金継ぎ(Kintsugi)は、壊れた器を修復し、再び使えるようにする日本の伝統的な技法です。
割れや欠けを「傷」ではなく「美」として生かすその思想は、世界でも高く評価されています。
しかし一口に「金継ぎ」と言っても、実は使う材料や工程によって複数の種類と方法が存在します。
ここでは、代表的な伝統金継ぎ(本漆金継ぎ)と簡易金継ぎ(モダン金継ぎ)の違いを詳しく解説し、
安全性や仕上げ方、初心者におすすめの金継ぎキットまで紹介します。
金継ぎの種類:伝統金継ぎと簡易金継ぎ

【伝統金継ぎ・簡易金継ぎの違い】の記事でも詳しく紹介しましたが、
現在、「金継ぎ」と呼ばれるものには大きく分けて2つの方法があります。
① 簡易金継ぎ(英名:Modern Kintsugi)
② 伝統金継ぎ/本漆金継ぎ(英名:Traditional Kintsugi、または単にKintsugi)
従来、漆芸の世界では「金継ぎ」といえば本漆を使う伝統的な方法を指しました。
一方で、エポキシ樹脂などを用いた簡易金継ぎは、短時間で手軽にできることから近年急速に広まり、
「モダン金継ぎ」として多くの方が楽しむようになっています。
現在では、どちらの方法も目的や価値観に応じて選ばれており、
金継ぎの文化をより多くの人に広げる大切な役割を担っています。
この記事では、両者の特徴や違いをわかりやすく紹介します。

① 簡易金継ぎ(モダン金継ぎ)
現代的な「モダン金継ぎ」は、エポキシ樹脂や合成接着剤を用いる方法です。
速乾性があり扱いやすいため、初心者でも比較的簡単に取り組めます。
工程を短縮できるため、器の修復にかかる時間は数日〜10日程度。短期間で完成できるのが魅力です。
また、近年では食品安全性を持つエポキシ樹脂も登場していますが、すべてが食品用というわけではありません。
硬化後の安全性は使用する製品によって異なります。
そのため、食器として使う場合は、使用する樹脂のメーカー情報を必ず確認することが大切です。
さらに、金継ぎされた部分は硬化後すぐに口に入るものではありませんが、
使用中に剥がれて小さな破片が口に入る可能性もわずかにあります。
そのため、つぐつぐでは口に触れる器には、伝統金継ぎ(本漆金継ぎ)を推奨しています。
モダン金継ぎは、観賞用の器や花器など「食器以外の用途」に向いています。
気軽に金継ぎの世界を体験したい方におすすめの方法です。
② 伝統金継ぎ(本漆金継ぎ)
「本漆金継ぎ」は、室町時代から続く日本の伝統的な修復技法です。
天然の漆(うるし)を接着・塗装の主材料として使い、
小麦粉や砥粉(とのこ)、金属粉など、主に自然由来の材料で構成されています。
漆は湿度と温度の条件下でゆっくりと硬化するため、完成までに1〜3か月ほどかかります。
その間、乾燥環境(漆風呂・むろ)の管理が重要で、伝統的な技法ならではの丁寧な工程を必要とします。
こうして仕上がった器は、漆器と同じく安全に食器として使用可能です。
仕上がりには深い艶と金属粉の輝きがあり、使うほどに風合いが増していきます。
つぐつぐでは、この伝統的な技法をできるだけわかりやすく現代化し、
初心者でも挑戦できるように工夫しています。
金継ぎの材料と食品安全性について
金継ぎに使用される材料は、「自然素材=安全」「合成素材=危険」と単純には言えません。
自然のものでも毒性を持つもの(例:ヒ素)がありますし、
一方で合成樹脂でも、完全に硬化すれば安全な製品は多く存在します。
つまり、金継ぎの安全性は素材そのものよりも、正しい知識と使い方に左右されます。
つぐつぐの考え方
私たちは、エポキシ樹脂も本漆も、それぞれの価値があると考えています。
しかし、金継ぎされた部分が剥がれて口に入る可能性を考慮し、
食器に使用する場合は伝統金継ぎをおすすめしています。
安全性だけでなく、「時間をかけて修復する体験」や「素材と向き合う過程」こそが
金継ぎの本当の魅力だと感じています。
金継ぎの仕上げ方と金属粉の種類

金継ぎの最終工程で使う金属粉には、粒の大きさや光沢の違いによっていくつか種類があります。
それぞれの特徴を理解して、目的や技量に合わせて選ぶことが大切です。
| 名称 | 特徴 | 難易度 |
|---|---|---|
| 消粉(けしふん) | 粒が細かく扱いやすく、初心者でもムラになりにくい。柔らかい光沢で自然な仕上がり。 | ★☆☆(初心者向け) |
| 平極粉(ひらごくふん/延粉) | やや粒が大きく、輝きが強い。慣れてきた方向け。 | ★★☆ |
| 丸粉(まるふん) | 粒が大きく金属光沢が強い。継ぎ目が平らでないとムラになりやすく上級者向け。 | ★★★ |
つぐつぐでは、食器にも安心な金・銀・プラチナの消粉仕上げを推奨しています。
また、観賞用として人気の真鍮粉も販売していますが、
こちらは食品安全試験を行っていないため、食器には使用しないようご案内しています。
初心者の方はまず「消粉」で金継ぎの美しさを体験し、
継ぎ目を平らに磨けるようになったら「丸粉」での挑戦もおすすめです。

自分に合った金継ぎを選ぶポイント
| 比較項目 | 簡易金継ぎ(モダン金継ぎ) | 伝統金継ぎ(本漆金継ぎ) |
|---|---|---|
| 主な材料 | エポキシ樹脂(合成) | 本漆(天然) |
| 完成までの期間 | 数日〜10日 | 1〜3か月 |
| 食器への使用 | 製品による(要確認) | 使用可(漆器同様) |
| 特徴 | 手軽・速乾・安価 | 奥深い光沢・耐久性・文化的価値 |
| 向いている人 | 初心者、観賞用、気軽に体験したい人 | 伝統技法を学びたい人、長く使いたい人 |
つぐつぐで学ぶ・楽しむ金継ぎ
つぐつぐでは、初心者から上級者まで幅広い方が金継ぎを学べる環境を整えています。
- 恵比寿・浅草教室
伝統金継ぎを基礎から丁寧に学べる教室です。少人数制で講師がしっかりサポート。
→ 最新情報・予約は以下の記事へ
- オンライン教室
2025年11月現在実施していますが、今後変更の可能性があります。
→ 最新情報・予約は以下の記事へ
- 金継ぎ検定
金継ぎ検定では、初級から最上級まで段階的に判定することで、
定期的に受けながらモチベーション高くスキルを磨くことができます。
→ 詳しくはこちら[外部サイトの検定ページへ]
自宅で始めるなら「つぐキット」
伝統金継ぎを、初心者でも自宅で安全に体験できるよう設計したのが「つぐキット」です。
必要な材料がすべて揃っており、食器に安心な本漆を使用。
日本国内向けはつぐつぐ公式オンラインストア、
海外からは専用通販サイトで購入できます。
→ 購入はこちら[つぐつぐ公式オンラインストアへ]
→ 購入はこちら[海外向け公式オンラインストアへ]


まとめ|修復から、あなた自身をつなぐ時間へ
金継ぎは、壊れた器を「元に戻す」ための作業ではありません。
思い入れのある器に込められた時間や記憶、人とのつながりに思いを馳せながら、
自分の手でゆっくりと直していく、そんな過程そのものを楽しむ文化です。
つなぐのは器の破片だけではなく、あなたの心かもしれません。
時間をかけて修復することで、器とともに自分自身も新たにつながっていく感覚を、ぜひ体験してみてください。
金継ぎ教室つぐつぐ お問い合わせ
気になること、ご質問がありましたら、下記までお問い合わせください!
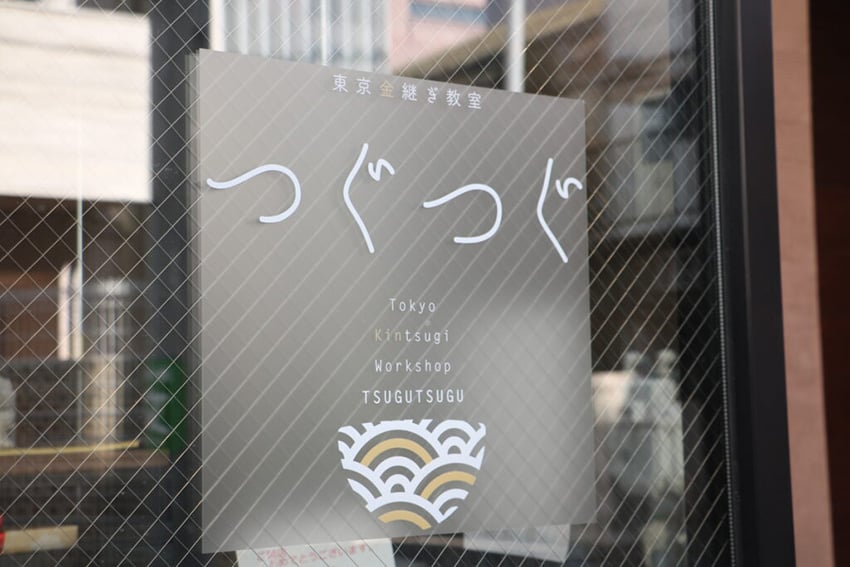
▼ 関連記事
コメント